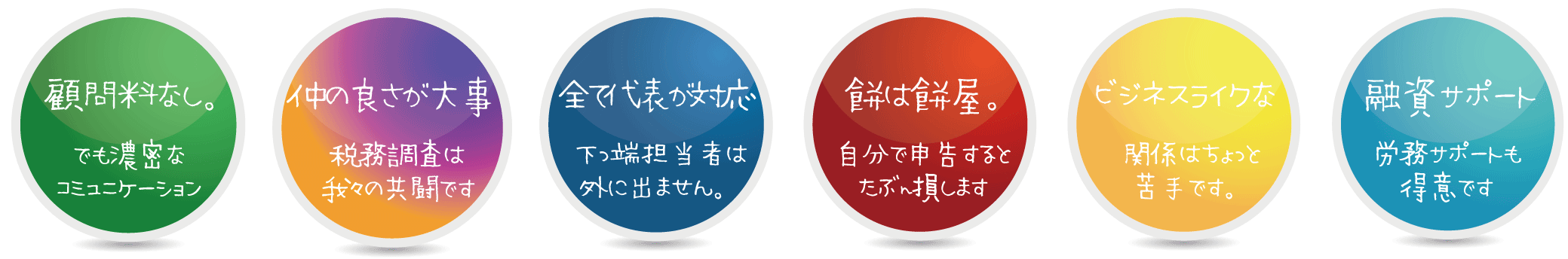この記事を要約すると・・・・
- 償却資産税の意味を知ろう
- LLPの意味を知ろう
- セーフティネットによる借入
こんにちは、副業専門税理士の佐藤です。
今回は「市町村から届く償却資産税って何だろう?」「共同で事業を展開している相手がいるばあいにどういう形態で行うべきだろう?」「地震や台風で業績が大幅に悪化した場合の対策をしたい」という経営者向けに書いてみました。しっかり読めば、償却資産税の納付漏れはなくなりますし、他人や他社との共同事業が容易になりますし、災害時への対策も行うことができます。
償却資産税申告書が送られてきました。これって何?
質問日:2009/06/10
設立1年目の会社経営者です。以前に来た償却資産税申告書をほったらかしにしてました。 償却資産税って意味が分からなかったからなんですが、これってどういうものですか?
償却資産税は固定資産税の一種と考えていればいいです!
回答日:2009/06/14
★固定資産税とは何でしょうか・・・
●固定資産税とは 1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に対し、 その固定資産の価格をもとに算定される税額を市町村に納付する税金です。 ●納税義務者 毎年1月1日現在の土地、家屋又は償却資産の所有者 ●固定資産税を納める人は・・ 土地→土地登記簿・土地補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人 家屋→建物登記簿・家屋補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人 償却資産→償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 <注意1> 年の途中で売買等による固定資産の所有権移転があっても、納税の義務は1月1日現在に 固定資産を所有する人にあります。 当事者間の合意で月割按分等の方法で両者が負担することは可能ですが、納税通知書は 1月1日現在の所有者に届きますね。 <注意2> 稼動休止中の資産の扱い 稼動中止資産であっても、必要な維持補修が行われており、いつでも動かせる状態に ある場合は減価償却資産に該当するものとすると、規定しています。 逆に保守管理を行わず、「ほったらかし」の場合には、減価償却を行えません。 この場合は、将来に渡り使用しない事に繋がるので「有姿除却」を検討すべきです。★では償却資産税とは・・・
<償却資産> 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、 減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得の計算上、 損金又は必要な経費に算入されるものです。 <申告> 償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の 内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに 申告する必要があります。 <償却資産の具体例> ①構築物 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、 ゴルフ練習場設備、変電設備、その他建築設備、内装・内部造作等 ②機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備等 ③船舶 ④航空機 ⑤車両及び運搬具 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等 ⑥工具、器具及び備品 パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、 金型、理容及び美容機器、衝立等 <償却資産から除かれるもの> ●自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトのように 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの ●無形固定資産(特許権、実用新案権等) ●繰延資産 ●骨董品など時の経過により価値の減少しない資産 ●耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で一時に損金算入したもの ●取得価額が20万円未満の償却資産で3年間で一括償却しているもの ●リース資産で取得価額が20万円未満のもの <でも以下の資産は申告対象です> ●簿外資産及び償却済資産でも、1月1日時点で事業の用に供することができるもの ●遊休・未稼働の償却資産でも、1月1日時点で事業の用に供することができるもの ●家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの ●耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満の償却資産でも個別に減価償却してるもの ●租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしている資産 (例)中小企業者等の30万円未満の少額資産の損金算入の特例を適用した資産
LLPってよく聞きますが何でしょうか?
質問日:2009/06/11
上場企業の経理担当者です。LLPという言葉を数年前からよく聞いていたのですが いまだに理解できません。簡潔明瞭に説明頂けないでしょうか?
LLPとは有限責任事業組合の略です!
回答日:2009/06/15
★有限責任事業組合=LLPとは何でしょうか ・・・
●LLP=有限責任事業組合という事業体の特徴 ①構成員全員が有限責任 ②損益や権限の分配を自由に決められる等、内部自治が徹底されている ③構成員課税(組織への課税はなし!出資者への利益分配に課税!) (LLP事業での損失は、一定の範囲内で出資者の他の所得と損益通算可能!) <注意1> 内部自治の徹底という日本語は分かりにくいですね。 簡単に言うと、組織の内部ルールが法律ではなく出資者同士の合意により決定できます。 これには2つの意味があります。 ①出資比率によらず、損益や権限の柔軟な分配ができるということ ②取締役などの会社機関が強制されず内部組織が柔軟 分かりますか? 対比するために株式会社を見てみましょう。 株式会社では出資比率に応じた損益分配等が強制されます(株主平等原則ですね)。 また、取締役や監査役の設置が強制されるんです。 <注意2> LLPの決算期末は任意に定めることができます。 構成員側の計算期間(個人の場合は12月、法人の場合は3月等)とLLPの決算期を ずらすことで、決算対策に余裕をもって取り組むことができます。★LLPを作るのはどんなとき!?
LLPは、法人や個人が連携して行う共同体として活用されています。 ■企業同士が連携して行う共同事業(共同研究、共同生産、共同物流など) ■ベンチャーと大企業の連携(バイオテクノロジーの研究開発など) ■異業種企業の共同事業(人工衛星の研究開発など) ■専門人材が行う共同事業(IT分野:ソフトウエア開発、経営コンサルティング等) ■起業家が集まり共同して行う創業★LLPの注意点
●個人構成員の税務処理はややこしい 法人と異なり、所得区分(利子所得、配当所得、事業所得、譲渡所得、一時所得、雑所得等) に収入・支出を分解して、個人所得税確定申告を行う必要があります。 つまり、個人構成員が存在する場合はLLPの決算作業は難しくなりますね ●有限責任でない場合がある LLPが融資を受ける際、構成員の個人保証がついて場合は有限責任ではないですね。 またLLPが行った行為に”悪意又は重大な過失”があると認められる場合、 第三者に対する損害賠償責任をLLPと連帯して負わなければなりません。 ●任意脱退も手間が増えます 組合員はやむを得ない場合を除き任意脱退ができませんが、 組合契約書で別段の定めをした場合は任意脱退できます。 LLPの構成員が多く、脱退が頻繁に発生すると、 その都度(仮)決算処理を行って、分配財産の計算を行う必要が生じますね。★LLPはこういうビジネスに最適!?
利益をシェアするという考え方当てはまる場合にはLLPは有効です。 いわゆる、プロフィットシェアですね。 これは法人組織では成立できないモデルです。 法人組織が事業活動から生じた利益を分配できるのは、 配当として法人税課税後所得を分配する場合ですね。 そして、個人の場合はその分配された配当に対しても所得税が課されるため、 手元には残る額は小さくなってしまいます。 しかし、LLPは構成員課税のため事業に参画している法人個人に 100%損益が還元されるのです。 最近では、副業を行う複数の人が寄り集まった場合にLLPを使うケースが出てきています。副業の人への税理士事務所としては共同事業においては是非利用してほしいです。
最近セーフティネットという言葉をよく聞きます。何?
質問日:2009/06/11
創業40年の老舗和菓子屋の経営者です。最近業績が悪化してきていますが、銀行から セーフティネットでお金を借りたら?と言われます。これってオトクなのでしょうか?
簡単に言うと低利率で借金できるということです!
回答日:2009/06/15
★セーフティネット保証制度
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により 経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度。 (保証料率は概ね1%未満)★対象となる中小企業者ってどんな人?
<要件①> 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、金融機関の破綻等により 経営の安定に支障を生じている中小企業者であること <要件②> 市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。 <例①> 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し 売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者。 ◆50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者 ◆50万円未満の売掛金債権だが、取引規模が20%以上である中小企業者 <例②> 業況の悪化している業種に属する中小企業者。 ◆最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上 ◆最近3か月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上★具体的な手続は???
市町村の窓口に認定申請書2通を提出(事実を証明する書面等の添付が必要)し、 認定を受けた後で、金融機関又は信用保証協会に認定書を持参し 保証付き融資を申込みます。