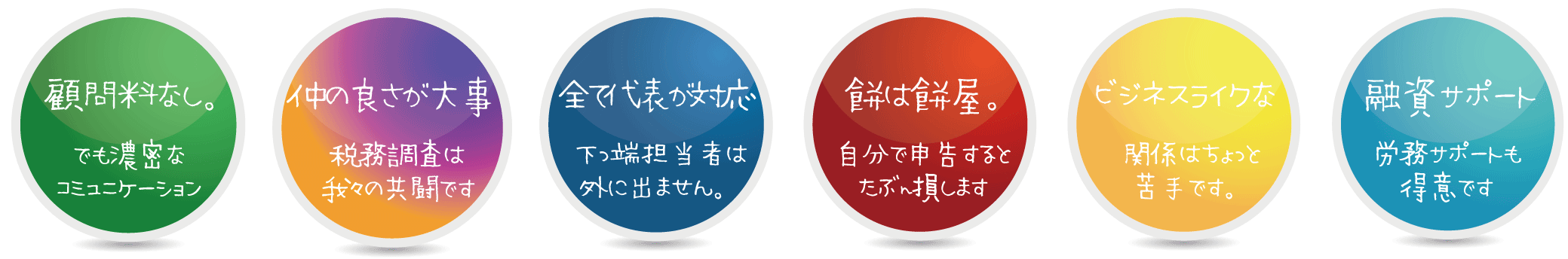固定資産の取得価額
固定資産を会社の事業に使用するためには、固定資産を購入し、会社等に運送し、それを使用できるまでに設置する等の活動が必要となります。
固定資産を会社の事業に使用するまでには、上記のような様々な活動が必要となることを考えると、会社の事業に使用する固定資産の価値は、単に「本体の購入価額」のみではなく、使用できる状況になるまでに発生した費用等も含まれると考えられます。
このため、法人税法では、固定資産の取得価額には、単に「本体の購入価額」だけでなく、固定資産を「事業に利用するまでにかかった費用」も含めて計算することを要求しています。
この固定資産を「事業に利用するまでにかかった費用」のことを、「附随費用」といい、具体的には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などがあります。
| 固定資産の取得価額 = 本体購入価額 + 附随費用 |
附随費用
附随費用の経費化の原則規定と例外規定
◆原則規定
附随費用については、原則として、「固定資産の取得価額」に含められます。
すなわち、附随費用を支払った時点で経費として計上するのではなく、固定資産の取得価額に含め一旦固定資産として計上されます。
その後、固定資産に係る減価償却を経て、経費として計上されます。
◆例外規定
法人税法上では、一部の附随費用については、「固定資産の取得価額」に含めず、附随費用を支払った時点で経費として計上することが認められています。
原則規定と例外規定の具体例
以下では、「必ず取得価額に含めなければならない附随費用」と「取得価額に含めないことも認められている附随費用(例外規定)」について、具体例を記載します。
| 取得価額に含める必要がある附随費用 |
| ・引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料 ・関税 ・その他購入のために要した費用 ・その資産を事業の用に供するために直接要した費用 ・固定資産の取得に関連して支出する地方公共団体に対する寄附等 ・土地、建物等の取得に際して支払う立退料 ・建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等で、当初から支出が予想されているもの (毎年支出することになる補償金は除かれます) |
| 取得価額に含めないことが認められる附随費用 |
| ・関税以外の租税公課 ⇒「不動産取得税」「自動車取得税」「新増設にかかる事業所税」「登録免許税」「その他登記または登録のために要する法定費用」など・登録費用 ⇒登記や登録にかかる「司法書士や行政書士に代行手数料」等 ・資産稼動前の借入金利子 ・割賦購入した固定資産に係る割賦利息部分 ・その他の経費 |
「少額な償却資産の取得価額」に対する判断基準
問題となる事項
減価償却に対しては「10万円未満の償却資産に対する全額経費計上の規定」、「20万円未満の償却資産に対する一括償却資産の特例」、「30万円未満の償却資産に対する全額経費計上の規定」があります。
このような規定を適用する場合には、固定資産の取得価額が「10万円未満」「20万円未満」「30万円未満」であるか否かが重要なポイントとなります。
ここで重要となることは、固定資産の取得価額を「どのような単位ごとで判断するか」が問題となります。
法人税法上の規定
この点、法人税法では、以下のような規定があります。
| 取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。 |
| 例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。 また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。 |
規定の内容
上記の本文の規定では、固定資産の取得価額は、「取引単位」で判断すると明文化されています。
ただ例示の規定では、「固定資産の機能する単位」で判断するとの考え方が示されています。
この点で、見解が争われることもありますので、少し注意が必要な点であると考えます。
耐用年数
固定資産の取得価額は、減価償却を通じて、その使用期間にわたって経費計上されます。
この「使用期間」のことを、「資産の使用に耐えることができる年数」という意味で「耐用年数」といいます。
減価償却の計算において、この「耐用年数」を会社の自由に委ねた場合には、その期間を長くしたり、短くしたりすることにより、減価償却費の金額を大きくしたり、小さくしたりすることができ、その結果、会社による利益操作が可能となります。
このような会社による利益操作の余地を防止するために、法人税法においては、「資産の種類」「構造」「用途」別に、耐用年数を詳細に定め、減価償却における会社の耐用年数の選択が画一的になされるようにしています。
このように、法人税法で規定される「耐用年数」を、特に「法定耐用年数」といいます。
耐用年数の選択にあたって留意すべき事項
耐用年数を会社が選択する場合に、注意しなければならない主要事項は以下のものです。
複数の用途で使用する資産の法定耐用年数について
資産の用途ごとに法定耐用年数が異なる場合で、その資産が複数の用途に使用されているときは、その減価償却資産の用途については、その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定して耐用年数を決定しなければなりません。
資産使用後に追加支出した部分に対する耐用年数について
資産を使用した後に、追加で改良等のために支出した部分については、当該部分を固定資産に計上し、本体と同じ耐用年数を選択して、減価償却計算を行う必要があります。
建物及び建物付属設備の耐用年数
「建物」「建物付属設備」の耐用年数を決定するにあたっては、
- 構造
- 用途
を把握して、その分類に応じた耐用年数を適用する必要があります。
以下では、「構造」「用途」を把握し、それに応じた耐用年数を選択する際に、注意すべき点を記載しております。
建物の構造についての留意点
建物の構造の判定
建物の構造を把握する場合には、その主要な「柱」、「耐力壁」、「はり」等のその建物の主要部分がどのような構造でかるかにより判断します。
⇒この判断にあたっては、建築業者から提出された見積書等に添付された「工事内訳書」等が参考となります。
2以上の構造からできている建物の構造の判断
一つの建物が2以上の構造により構成されている場合は、構造別に区分することができ、かつ、それぞれが別の建物とみられるものであるときは、その建物については、それぞれの構造の異なるごとに区分して、その構造について定められた耐用年数を適用します。
⇒例えば、鉄筋コンクリート造り2階建の建物の上に、木造建物を建築して3階建としたような場合が該当します。
建物の内部に施設されたものの構造判断
建物の内部に施設されたモノについては、そのモノの構造が当該建物の骨格の構造と異なっている場合においても、それを建物の本体と区分することはせず、建物本体に含めて、建物の耐用年数を適用します。
⇒例えば、鉄筋コンクリート造の建物について、その内部に木造の内装等を施設した場合には、当該内装部分を建物から分離して、木造建物の耐用年数を適用することはできません。木造内装部分についても、建物本体の構造に従った耐用年数を選択することが必要となります。
建物の用途についての留意点
2以上の用途に使用される建物に適用する耐用年数の特例
1つの建物を複数の用途に使用するために、建物の一部について特別な内装等の施設をしている場合には、当該建物についてその用途について定められている耐用年数をそれぞれ適用することができます。
⇒例えば、 例え鉄筋コンクリート造の6階建のビルディングのうち1階から5階までを事務所に使用し、6階を劇場に使用するため、6階について特別な工事等をしている場合には、1階から5階までの部分の耐用年数と6階部分の耐用年数を分けて、それぞれについての耐用年数を選択できます。
ただし、鉄筋コンクリート造の事務所用ビルディングの地階等に附属して設けられている電気室、機械室、車庫又は駐車場等のようにその建物の機能を果たすために必要な補助的部分については、これを用途ごとに区分しないで、当該建物の主たる用途について定められている耐用年数を適用する必要があります。
内部造作を行わずに賃貸する建物
建物のうち、その階の全部又は適宜に区分された場所を間仕切り等をしないで賃貸し、間仕切り等の内装については貸借人が施設している建物については、「その賃貸の用に供している部分の用途」の判定については、「左記以外のもの」に該当するものとする。