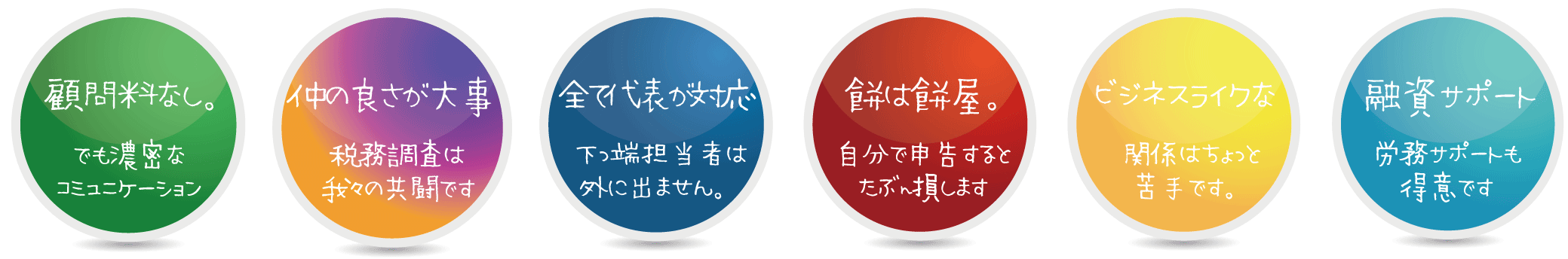結婚・出産祝金に対する所得税の課税・非課税範囲
規定
結婚祝金を会社等から従業員に支給した場合の所得税の課税・非課税規定には、以下のようなものがあります。
| ・使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とされます。 ’ ・ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えないとされています。 |
規定の趣旨
結婚祝金や出産祝金は、役員または使用人としての地位に基づいて会社から支給されるものですので、原則として、給与所得に該当することになります。
しかし、このような祝金品の贈答は、使用者と役員または使用人の問に限らず、広く社会的慣習として一般に行われているものであることを考慮すると、その祝金品として常識的な金額のものまで課税するのは妥当でないことから、「社会常識に照らし相当な金額のもの」には所得税を課税しないというものです。
所得税が非課税となるための要件
所得税が非課税となるためには、以下のような要件を充たす必要があります。
①会社と役員・従業員との雇用契約等に基づいて支給されるものであること
②広く社会的慣習として一般に行われているような「結婚・出産等の祝金品」の支給であること
③特定の者のみに支給されるのではなく、要件に該当すれば支給基準等によりすべての役員・従業員が対象となっていること
③その金額が受給者の地位に照らして、社会通念上相当と認められること
社会通念上相当と認められる金額以上の場合
| 税務調査等により、結婚祝金や出産祝金が社会通念上相当とみとめられる金額以上であると指摘された場合には、結構祝金や出産祝金の全額が所得税の課税の対象となる可能性があります。 |
祝金から、社会通念上相当と認められる金額を引いた残額に対してのみ、所得税が課税されるものではありません。
これは、この規定が、「本来的には給与等として所得税の課税対象となるものを、社会通念上相当額と認められるものに限定して、所得税が非課税としてもよい」という規定であるため、社会通念上相当額と認められない場合には、その全額が課税される可能性があります。
その他の祝金対する所得税の課税・非課税範囲
その他の祝金の種類
会社では、下記のような祝金を支給する場合も考えられます。
・従業員に対する成人祝金
・役員・従業員の子供等の入学祝
・役員・従業員の自宅新築祝い、海外出張祝い など
所得税の課税・非課税範囲
所得税が非課税となるか否かについては、
①広く社会的慣習として一般に行われているか
③支給基準等によりすべての役員・従業員が対象となっているか
③その金額が受給者の地位に照らして、社会通念上相当と認められているか
を勘案する必要があります。
この点、従業員自身の成人式祝金や従業員の子供等の入学金等については、社会的慣習として一般に行われているとも考えられます。
他方、従業員等の自宅新築祝、海外出張祝等については、あまり支給している会社は少ないのではないかと考えられます。
これらについて、所得税を非課税扱いしようとする場合には、上記の要件をしっかりと検討することが必要と考えます。
所得税が課税された場合のリスク
1、所得税法上のリスク
上記の金額について、税務調査等により所得税の非課税扱いが否認された場合には、これらの支給額が給与・役員報酬とされてしまいます。
給与や役員報酬として扱われた場合には、会社に源泉徴収義務が発生し、結果、源泉徴収漏れとなってしまいます。
この源泉徴収漏れについては、会社に「不納付加算税」や「延滞税」の納付が必要となるリスクが出てきます。
2、法人税法上のリスク
上記の金額については、通常、会社では、「福利厚生費」として法人税法上損金に計上してる場合が多いと思います。
この支給が役員への「福利厚生費」として計上されている場合で、税務調査等によりこれが役員報酬と認定されてしまうと、法人税法における損金算入否認のリスクが生じます。
役員報酬は、法人税計算において、「毎月一定金額を超える支給額」については、損金として認められないために、法人税に係る税金が追加徴収される可能性があります。
会社が、役員や従業員に対して支給する祝金に対して、所得税を非課税扱いする場合には、上記のようなリスクが存在します。
このため、所得税の取り扱いが不明確なものについては、しっかりと事前に検討しておくことが必要であると考えます。
葬祭料、香典、見舞金の所得税の課税・非課税
所得税法の規定
| 葬祭料や香典、災害等の見舞金※は、その金額が社会通念上相当と認められるものであれば、所得税は課税されません。 |
※見舞金については、災害見舞金だけでなく、傷病見舞金として支給されるものも含まれると解釈されます。
‘
規定の趣旨
本来、会社から役員・従業員に支払われた弔慰金は、支給を受けた人の給与所得となります。
ただ、日本においては、弔慰金支給は、広く一般に認められた社会的慣行であり、一種の儀礼的な行為と認められています。
したがいまして、弔慰にふさわしい金品の受領について課税するのは妥当でないとし、社会通念上相当と認められる場合には、これに係る所得税が非課税となります。
社会通念上相当と認められる金額以上の場合
| 税務調査等により、弔慰金が社会通念上相当とみとめられる金額以上であると指摘された場合には、弔慰金の全額が所得税の課税の対象となる可能性があります。 |
弔慰金から、社会通念上相当と認められる金額を引いた残額に対してのみ、所得税が課税されるものではありません。
これは、この規定が、「本来的には給与等として所得税の課税対象となるものを、社会通念上相当額と認められるものに限定して、所得税を非課税としてもよい」という規定であるため、社会通念上相当額と認められない場合には、その全額が課税される可能性があります。
社葬費用に対する所得税の課税・非課税の範囲
法人税法の規定
所得税法上での社葬費用について直接規定した規定は存在しませんが、
法人税法上では、社葬費用については、以下の規定が存在します。
| 法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。 |
【上記規定の所得税法での読み方】
上記法人税法の規定は、「上記の範囲での社葬費用は、法人が直接費用として計上してもよい。」という規定です。
このことは、反面、「上記の範囲での社葬費用を会社等が支払ったとしても、死亡した役員や使用人の遺族等の所得としなくてもよい。」ということを規定しているともいえます。
社葬を行うことが社会通念上相当と認められる場合
社葬を行うことが社会通念上相当と認められる場合とは、以下のような事情を勘案して、会社が社葬を行うことに十分な理由が存在する場合をいいます。
| 故人の生前における会社への貢献度(会社における経歴、職務上の地位)や死亡事情(業務上、業務外の区別)や会社の規模等に照らし、会社が社葬費用を負担するに足る十分な理由があれば、会社が社葬を行う十分な理由が存在すると言えます。 |
【留意事項】
会社への貢献がないにも関わらず、役員や従業員の親族であるという理由だけで社葬を行っても、会社がそれを直接費用計上することは認められません。
このような場合には、会社が支出した社葬費用は、一旦「役員への報酬」や「従業員への給与」として扱われ、支給を受けた役員や従業員が個人の費用として葬儀費用を支払ったとして扱われます。
葬儀費用が「役員への報酬」「従業員への給与」として扱われてしまうと、会社にそれらに係る源泉徴収義務が生じます。
源泉徴収を行っていない場合には、源泉徴収漏れの責任として「不納付加算税」や「延滞税」が徴収されるリスクが生じます。
また、「役員への報酬」として扱われると、この金額は「役員への不定期役員報酬」として、法人税法上、会社での費用処理が否認されるリスクが生じます。
通常要すると認められる金額
社葬のために通常要すると認められる費用としては次のようなものが考えられます。
(1) 社葬の通知費用
(2) 葬儀会場や祭壇等の使用料
(3) 僧侶へのお礼
(4)供花、供物、花輪、樒の費用 運転手、葬儀委員への心付け
(5) 社葬に参列する人の案内や警備、車の交通整理等に要する人件費
(6)遺骨、遺族、来賓者の送迎費用
(7) 会葬者に対する礼状、粗品等の費用など
一方、明らかに故人の遺族が負担すべきであり、社葬のために通常要する費用にあたらないものとしては次のようなものが考えられます。
(1) 密葬や通夜の費用
(2) 遺体の火葬費用
(3) 戒名を受けるための費用
(4) 仏壇や位牌の購入費用
(5) 墓地、墓石の購入費用(永代使用料を含む)
(6) 香典返しの費用など